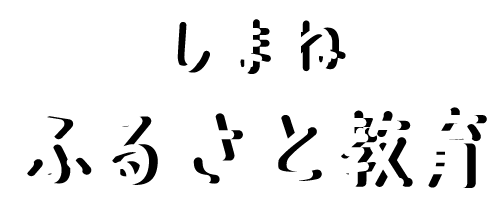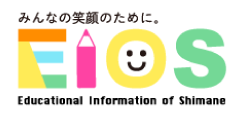筍掘りと筍を使った調理活動
〔活用した教育資源〕斐川・出西の筍山(斐川町)
ねらい
地域の山での筍掘りやその筍を使った調理活動を通して、地域の自然を感じるとともに、自らの体験の幅を広げたり人と共に活動する喜びやよさを味わったりする。
1 取組の概要
1)バスで斐川町の筍山に移動し、筍山オーナーから筍の掘り方や注意点を聞く。
2)範囲と時間を決め、鍬やスコップを使って見つけた筍を掘る。学校に戻り皮むきをする。
3)日を置いて調理活動をする。各班で、筍ご飯や筍を使ったおかず等を作る。
4)筍の香りや食感を味わいながら、皆で筍料理をいただく。片づけも皆で協力して行う。
5)自分の言葉で感想を述べ合う。筍山オーナーへのお礼メッセージを書く。
2 ふるさとの「ひと・もの・こと」をどのような力を付けるために、どのような意図をもって活用したか。
※若松分校は県内各地から医療的関わりを必要とする子どもたちが集っているため、市のふるさと教育本来の意図を意識しつつ、若松分校独自の視点に置き換えて活用している。
(ふるさとへの愛着や誇り、貢献意欲の視点から)
〈若松分校「育てたい力」より〉
A4;感動する心 (1)周りの美しさ(自然・芸術など)に気づくことができる
C4;人とともに動いたり協力したりする力 (1)同じ目的をもって人と一緒に作業ができる
E1;やってみようとする力 (1)不安や心配があっても最初の一歩が踏み出せる
1)島根の自然に関わる機会をつくる
毎年お世話になっている斐川町青木様所有の筍山で筍掘りができるよう、早めにお願い及び、打ち合わせをしておく。体験の少ない子どもたちが自然の筍に触れたり掘ったりすることで、感動や発見、気づきが得られるようにする。
2)筍を掘る活動、その筍を使って調理する活動の両方を用意する
筍を掘る活動では、筍掘り自体が初めての子もいるため、一人一人の子どもに対応するスタッフを決めておき寄り添いながら活動を行う。そして、子ども自身が自分で筍を発見したり、自分で掘り起こしたりする体験ができるようサポートする。調理活動では、グループ構成を事前に相談したり、簡単なレシピや分担表を用意したりすることで、コミュニケーションに不安がある子どもでもその子なりに活動に参加できるようにする。そして、自分が掘った筍のおいしさや、人と協力して一緒に活動できたことの喜びを少しでも味わえるようにする。
(学力育成の視点から)
〈若松分校「育てたい力」より〉
D2;話を聞く力 (1)人の話を最後まで聞くことができる
D1;自分の思いや考えを人に伝える力 (4)自分の考えや思いを人に伝えることができる
(7)集団の中で発言(発表)することができる
1)分校スタッフからだけでなく、筍山オーナーからの話を聞く時間を設定する
筍を大切に育て、また筍掘りについて熟知しておられる地域の大先輩からの話をしっかり聞くことで、活動の意義やポイントをつかませる。
2)自分の思いを他者に伝える場面を設ける
発表の内容や量は問わず、「パス」もありとした上で、活動を通して感じた思いを可能な限り自分の言葉で述べる場面をつくる。他者の言葉を聞いて感じた新たな思いも大切にする。こうしたミニ発表の場を積み重ねることで、自信や自己肯定感を少しずつ高めていく。また、筍山オーナーに対するお礼メッセージ書きを通して、お世話になった離れた場所におられる相手に対する感謝の気持ちを自分の言葉で伝えることのよさも感じられるようにする。
3 児童・生徒に見られた変容(どのような力が身に付いたか等)
(ふるさとへの愛着や誇り、貢献意欲の視点から)
1)自生の筍を自分で発見し、体を動かして掘り、それを調理して口に入れるという一連の活動を通して、子どもたちは自然の恵みのすばらしさや豊かさを感じ取っていた。家庭でも作ってみたいという思いを持つ子や、実際に家庭で筍料理を作った子もいた。
2)筍山オーナーと共に活動することで距離が縮まり、自分から話しかける子どもの姿が見られ た。また、一緒に掘ってくださったことに嬉しさを感じたり感謝したりする場面があった。
3)段階を踏んだ活動を組むことで、苦手意識のある子どもも参加することができた。振り返りでは、活動に対して肯定的な思いを持つことができた。
(学力育成の視点から)
1)筍山オーナーのお話をしっかり聞いてから筍掘りに挑むことで、筍を発見したり、上手に筍を掘り返したりすることにつながり、全員が達成感をもつことができた。
2)発言や発表の苦手な子どもが多い中、実際に体験をした後では、自然に感動や喜び、感謝を口にする子どもが多くいた。共に体験した仲間がいることで、自分の思いを共感的に受け止めてもらえる体験にもつながった。年間を通して、このような場や機会を計画的に設定し、子どもたち一人一人の自信や力を少しずつ高めることを目ざしている。
4 課題や今後の展望
1)さまざまな実態の子どもたちが、少しでも活動への参加や他者との関わりの幅を広げるためには、どう活動を計画し実施していけばよいのか、年度ごとに検討し練り直していく必要がある。限られた支援者数の中、子どもに実態に応じた合理的配慮のあり方も引き続き探っていきたい。
2)県内の様々な場所(年度によっては県外からもある)から来ている子どもたちに「ふるさと教育」の意義を感じさせていくことへの難しさがある。その中で、若松分校の「育てたい力」との関連の中で、今できることや目の前の子どもたちに必要だと思うことを積み重ねていくことを大切にしている。子どもたちの成長の先に、それぞれの場所での「ふるさと」への貢献があると信じて、今後も子どもたち一人一人の自信回復、自己肯定感向上を目指し、多職種連携のもと活動を計画・実施していきたい。
- テーマ
- ふるさと教育
- 学校区分
- 小学校・中学校
- 教科
- 自立活動
- 関連する教科
- 学年
- 小学1年
- 関連する学年
- 小学1年 小学2年 小学3年 小学4年 小学5年 小学6年 中学1年 中学2年 中学3年
- 学校名
- 出雲市立神戸川小学校・河南中学校若松分校
- 所管部門
- 出雲教育事務所