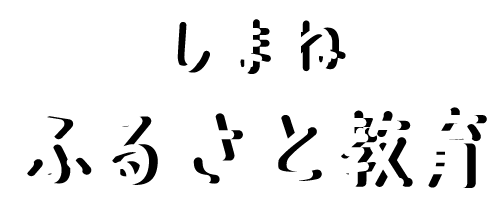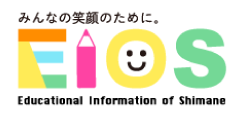Act「自分たちができること」
〔活用した教育資源〕地域の企業、産業、政策、講師
ねらい
○日常生活や身近な実社会にある課題を見つけ、課題解決のために「自分たちができること」を考える。
○課題解決に向けて主体的に行動し、地域や社会の一員として貢献していこうとする態度を育てる。
1 取組の概要
(1)オリエンテーションを行い、SDGsに関する出雲市内の企業の取組を知る。
(2)学級で取り組むテーマを決める。(食品ロス、ゴミ問題、エネルギー問題 など)
(3)学級で決めたテーマごとに、課題解決に向けた行動案を出し合い、決定する。
(4)Act(行動)する。
(5)学級内で成果や課題をまとめる。(個人:キャリアパスポート)
(6)学年で活動報告会を行う。
2 ふるさとの「ひと・もの・こと」をどのような力を付けるために、どのような意図をもって活用したか。
(ふるさとへの愛着や誇り、貢献意欲の視点から)
自分たちも関われる身近な問題として意欲的に課題設定に取り組めるように、出雲市内の企業でもSDGsへの取組が行われていることを知らせ、自分でも調べる学習を取り入れた。また、課題解決に向けて実際に「行動する」ことを中心として活動することで、主体的・協働的な探究学習へとつなげることができた。通学路や公園といった身近な場所や、日頃よく利用する店舗や給食センターにSDGsの観点から目を向けて、そこで思いを持って働く人の姿に触れることで、自分自身の将来やふるさとの未来について改めて考え、よりよい地域づくりのために貢献していきたいという意欲を高めることができた。
(学力育成の視点から)
自分で課題を設定し、情報の収集・選択を行い、整理・分析してまとめ、表現するという探究的な学習に必要な資質・能力の育成につながった。学級ごとにテーマを設定する学習活動では、友達と意見を出し合い、自分たちで課題設定やその解決法を検討するなど、主体的で協働的な学習ができた。また、家庭科や社会科といった各教科で学んだことを活用しながら、自己の生き方まで考えるなど、教科横断的な学習となった。身近な地域や自分たちの日常生活の中にも、フード・ロスやゴミ問題といった社会問題やフード・ドライブやリサイクル活動といった様々な対策があることを知り、生徒一人一人が明確な課題意識を持ち、主体的に行動することにつながった。
3 児童・生徒に見られた変容(どのような力が身に付いたか等)
(ふるさとへの愛着や誇り、貢献意欲の視点から)
これまで知っているようで実は知らなかったふるさとの良さや課題について、SDGsの視点から改めて捉え直すことができた。また、自分たちで考えた課題解決策を実行に移すことで、地域の方に喜んでもらえたり、校内で他学年の生徒や教職員の意識を高めることにつながったりするなど社会や地域に貢献することの意義を感じた生徒も多く見られた。生徒の振り返りの中には、「今回のActを日常生活の中でも続けていきたい。」、「もっと別のActにも挑戦してみたい。」などといった意見が見られ、今後も自分にできる形でふるさとを大切にしていきたいという思いをもつことができた。
(学力育成の視点から)
学級ごとのテーマ設定を行うために、SDGsについてタブレットを使ってインターネット検索を行ったり、KJ法を使って様々な意見をまとめたりすることができた。Actを行った後、個人で振り返りをするだけでなく、成果や新たに見つけた課題を学級内で発表し合い、さらには学年全体で活動報告をして共有することで、より広い視野で地域のためにできることを考えていこうとするなど、主体的に学習に取り組む姿が見られた。
4 課題や今後の展望
○今回の学習活動を通して感じた意欲やモチベーションをこの場限りにするのではなく、今後の日常生活の中でも、ふるさとのために自分ができることを実践していきたいという思いを継続していけるような手立てを考えていきたい。
○1年生で学習したことを、2年生、3年生へと継続していけるように、学年に応じた系統立てた学習計画を検討する必要がある。
○体験活動や地域に出かけての学習活動が増えると、それに関わる教職員の数も必要になるが、各学
年部の教員だけでは対応しきれない場合も考えられる。学校としてどのような体制を考えていくべきか、検討事項である。
- テーマ
- ふるさと教育
- 学校区分
- 中学校
- 教科
- 総合的な学習の時間
- 関連する教科
- 学年
- 中学1年
- 関連する学年
- 学校名
- 出雲市立第一中学校
- 所管部門
- 出雲教育事務所